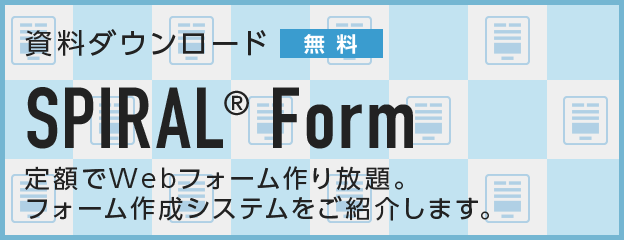Webフォーム作成の記事
ARTICLE問い合わせ対応を効率化しよう!原因や業務負担を減らす方法を解説
企業規模が大きくなりつつある企業では、問い合わせ件数の増加に伴い、業務負担が大きくなっているとお悩みではないでしょうか。しかし、具体的に何が原因になっており、どのように改善していくべきかわからずお困りのご担当者様も多いでしょう。この記事では、問い合わせ対応を効率化する方法について、事例や注意点も含めてわかりやすく解説します。
目次
難しい問い合わせ対応業務を効率化すべき理由

近年、問い合わせ対応業務の多様化・複雑化が進み、従来の人力での対応だけでは時間も人員も不足するようになりました。
そこで重要となるのが、問い合わせ対応の効率化です。まずは、効率化に取り組むべき理由を2つに分けて紹介します。
【理由1】担当者の負担軽減につながる
問い合わせ対応業務を効率化する最大の目的の一つは、現場で働く担当者の負担を軽減することです。
たとえば、従来の電話やメール対応では、同じような質問に何度も時間を取られたり、複雑な問い合わせの調査に追われたりするなど、担当者一人ひとりにかかる負荷が大きいという課題がありました。
こうした非効率な状態を放置すると、担当者の疲弊やモチベーション低下を招きかねません。
業務を効率化することで、1件あたりの対応時間を短縮し、手作業による繰り返し業務や長時間労働から担当者を解放することができます。これにより、より付加価値の高い業務に集中できる環境が整い、生産性の向上にもつながります。
また、問い合わせの現場では、次のような対応の影響で、精神的な負荷につながるケースも少なくありません。
- クレーム処理を含む複雑な質問
- 短時間での対応
上記を放置すれば、離職率が上がり対応力が低下します。これらの対応も効率化をすることで従業員の健康を守り、離職防止にもつながるでしょう。
【理由2】顧客満足度を向上させられる
問い合わせ対応の効率化は、単にスピードを上げるだけでなく、「顧客体験(CX)の質」を向上させます。
特に、複雑で難しい問い合わせに対して、担当者が調査に時間を取られ、回答が遅れたり、たらい回しにされたりすることは、顧客満足度を著しく低下させる原因となります。
効率化によってナレッジ共有の仕組みなどを整備すれば、担当者は難しい質問にも迅速かつ正確に回答できるようになります。スムーズな問題解決は顧客の信頼獲得に直結し、結果として企業全体の評価を高めることにつながるのです。
問い合わせ対応が「非効率」になる3つの原因

効率的な問い合わせ対応ができていないと、顧客満足度の低下や従業員の負担増につながります。
特に近年は、問い合わせ件数の増加やチャネルの多様化により、従来のやり方では限界を迎える企業も少なくありません。ここでは、非効率化の代表的な3つの原因を解説します。
【原因1】問い合わせ件数が年々増加している
対応できるリソースが限られているのにもかかわらず、問い合わせ数が増加するような状況は、非効率化を招く最大の原因です。実際、多くの企業では次のような問い合わせの増加が起きています。
- セールやキャンペーン時期に通常の2〜3倍の問い合わせが殺到する
- サブスク型サービスで契約変更や請求関連の質問が急増する
人力中心の対応だけでは限界があり、同じ対応を続けると非効率化につながるかもしれません。すでに非効率化が起きている場合には、ツール導入や体制改善が不可欠です。
【原因2】人手不足・担当者のスキルの属人化が進んでいる
人材不足と業務の属人化は、次のように問い合わせ対応の品質とスピードを低下させる原因になります。
- ベテラン不在時に対応品質が急落する
- マニュアルが不十分で、新人が効率的に対応できない
- 同じ内容でも担当者によって回答が異なると顧客からの信頼を損なう
たとえば現在、日本全体で人材不足が深刻化しています。帝国データバンクが公開している以下の企業調査によると、51.4%の企業が「正社員不足」であるとわかっています。
正社員不足の企業は51.4%、非正社員では30.0%と高止まり
慢性化した人手不足は、深刻な「高止まり」状態が続いている。2025年4月時点における、正社員の人手不足を感じている企業は51.4%だった。
出典:帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2025年4月)」
【原因3】チャネル・ツールが分断されている
複数のチャネル(問い合わせの経路)を統合管理できていないことが、対応効率を下げる原因になる場合もあります。
特に、次のような窓口ごとに情報を個別管理していると、顧客ごとの問い合わせ履歴が分断され、同じ顧客に何度も同じ説明をさせてしまうなど、CXを損ねるかもしれません。
- 電話
- メール
- チャット
- SNS
問い合わせの見逃しによって苦情を受ける、過去履歴を確認できず顧客が同じ説明を繰り返す負担を負うといったトラブルにも発展するため、CRMや統合管理システムを導入してチャネルを一元化するといった対策が必要です。
問い合わせ対応を効率化する6つの方法・コツ
問い合わせ対応を効率化する際には、「問い合わせ件数を減らす」「対応時間を短縮する」「従業員の負担を減らす」といった視点で対策を考えることが重要です。
ここでは、企業が取り組むべき6つの方法を紹介します。
【効率化1】対応マニュアル・テンプレートを整備する
誰が問い合わせ対応をしても同じ品質を維持できるようにしたいなら、マニュアルとテンプレートを準備しましょう。
対応フローが統一されれば、新人教育の時間を削減できるほか、オペレーターごとの品質差をなくせます。さらに会話用のテンプレートを用意すれば、熟練オペレーターと同等の品質を再現可能です。
【効率化2】FAQページを充実化させる
問い合わせ件数を減らす目的で効率化を進めたいなら、FAQページを充実化することが欠かせません。
FAQのページを用意すれば、顧客が問題や不安を自己解決できるようになります。たとえば、次のような施策でFAQの項目を追加・更新していきましょう。
- アクセス数の多い質問を定期的に更新して最新化する
- サイト内の検索機能やカテゴリー分けを改善する
- 図解や動画を活用した解説を加えて、理解を助ける
顧客が自ら疑問を解決できれば、オペレーターへの依存度が下がり、業務負担を大幅に削減できます。社内リソースを増やせない場合には、FAQページを活用するのがおすすめです。
【効率化3】ヘルプセンターを活用する
FAQよりも幅広い情報をまとめた「ヘルプセンター」を整備すれば、顧客が自分で問題を解決できる割合を高められます。
ヘルプセンターとは、商品やサービスに関する疑問や問題をユーザーが自力で解決できるよう、企業が提供するオンラインのサポートサイトのことです。
ヘルプセンターを導入すると「顧客が1人で解決できる→問い合わせ件数が減る→オペレーターは高度な案件に集中できる」という好循環を生み出せます。
【効率化4】チャットボット・AI応答ツールを導入する
24時間365日いつでも問い合わせサポートをできるようにしたいなら、チャットボット・AI応答ツールを導入するのがおすすめです。
AIは履歴を学習して、精度の高い回答を自動で返すため、かんたんな質問はAIに任せて、オペレーターは複雑な問い合わせだけに専念できます。
学習させる手間はかかりますが、一部の質問に対し自動返答ができるようになるため、これまで人力で対応してきた問い合わせ対応の負担を削減可能です。
【効率化5】問い合わせ管理ツール(CRM)を導入する
複数チャネルからの問い合わせを一元的に管理したい場合には、CRM(顧客関係管理システム)の導入がおすすめです。
まず、電話・メール・チャット・SNSなど異なる窓口を個別に管理していると、対応漏れや重複対応が起こりやすく、顧客満足度を下げる原因になります。対してCRMを導入すれば、顧客情報や対応履歴を一元管理でき、誰が対応してもスムーズに進められます。
顧客の満足度向上と業務効率の改善を同時に実現できるため、特に問い合わせ件数が多い企業や複数チャネルを運用している企業はCRMの導入がおすすめです。
【効率化6】社内ナレッジの共有・可視化に取り組む
担当者ごとに対応品質がばらつく場合には、社内ナレッジの共有・可視化に取り組むことがおすすめです。
対応ノウハウが属人化していると、新人は同じ質問に時間をかけてしまい、顧客満足度が低下する恐れがあります。対してナレッジを全員で共有すれば、誰でも一定の品質でスムーズに対応できるようになります。
社内Wikiやナレッジベースに事例を蓄積することで、新人でも短期間で即戦力になれるのが魅力です。人手不足や教育コストを課題に感じている場合には、ナレッジ共有の仕組み導入がおすすめです。
企業が実施している問い合わせ対応の効率化事例

ここでは、実際に問い合わせ対応の効率化を実現した2つの事例を紹介します。
【事例1】管理の一元化で対応時間を削減
ある物流系の企業では、多言語対応の問い合わせ管理システムを内製しました。
従来は広報部が全ての問い合わせメールを振り分けていたため、負担増加と返信遅延が課題でしたが、導入後は自動振り分けやステータス管理により、対応漏れを防ぎつつ、対応時間を約90%削減しています。
また、多言語対応の問い合わせ管理システムで海外顧客の離脱も減少し、顧客接点の強化につながりました。
【事例2】問い合わせ対応のデジタル化で業務拡大
派遣プログラムを提供しているNPO法人は、海外派遣プログラム参加者の申込管理をツール導入でデジタル化しました。
従来は申込データ入力やメール対応などに業務時間の半分を費やし、拡大に対応できない状況でしたが、導入後はマイページ機能で申込・履歴を一元管理でき、通知機能により対応漏れを防止しています。
業務時間が半減したほか、返信スピードを従来の1/5まで短縮しています。
効率化対策やツール導入時に確認すべきポイント

問い合わせ対応を効率化するためにツールを導入する際は、やみくもに選ぶのではなく、自社に合った仕組みかどうかを見極めることが大切です。
ここでは特に重要な3つのチェックポイントを紹介します。
【チェックポイント1】自社の課題にマッチしているか
効率化ツールを選ぶ際は、まず自社の課題に直結しているかを確認しましょう。
たとえば「問い合わせ件数が多すぎる」のか「担当者の負担が大きい」のかで選ぶべきツールは変わります。
課題を明確にすれば、無駄なコストを防ぎ効率化を最短で実現できます。
【チェックポイント2】既存業務との連携性が高いか
どんなに高機能なツールでも、既存の業務フローやシステムと連携できなければ活用が進みません。
特に、CRMやチャットボットなどは、社内の顧客管理システムやFAQページとの統合が必須です。導入前に連携の可否を確認することで、情報の分断を防ぎ、円滑なオペレーションを維持できます。
【チェックポイント3】操作性とサポート体制が充実しているか
ツールを選ぶ際には、使いやすさのチェックが重要です。
もし操作が複雑だと現場での浸透が進まず、むしろ非効率になることがあります。また、UIの使いやすさに加え、導入支援やトラブル対応のサポート体制が整っているかも重要です。
問い合わせ対応を効率化するおすすめフローチャート

問い合わせ対応業務を効率化するうえで、効果的な手法のひとつがフローチャートによる可視化です。
たとえば、顧客からの「商品不良」の問い合わせが入った際に、オペレーターが一次対応 → 技術部門に確認 → 返品対応部署に引き継ぎ → 顧客への最終連絡、という流れをフローチャートで示すと、対応担当者以外でも流れを即座に把握できます。
以下に、フローチャート作成の基本手順をまとめました。
- 対象業務を明確化する
効率化が必要な業務を特定する - 担当部署・担当者を抽出する
営業・サポート・発送などを洗い出す - 作業内容を細分化する
対応開始から完了までを具体的に書き出す - 時系列で整理する
開始・終了を明示し、矢印で流れを可視化 - 実際にフローチャートを図化する
スイムレーンや図形を活用して見やすく設計
近年は、メール・チャット・SNSなど問い合わせチャネルが増えたことで業務は複雑化しています。フローチャートを用いれば、対応の属人化を防ぎ、誰でもスムーズに対応できる体制をつくり出せます。
フローチャートは社内問い合わせ対応にも活用可能
フローチャートは顧客対応だけでなく、社内問い合わせ対応にも有効です。
たとえばIT部門へのPC不具合相談や人事への勤怠関連の質問なども、フローチャートで「どの部署に問い合わせるか」「必要な申請書はどこにあるか」を可視化することにより、社員が迷わず自己解決できます。また、その準備が総務や情報システム部門の負担軽減にもつながります。
問い合わせ管理・対応の効率化はツール導入がおすすめ

すぐに問い合わせ対応を効率化したいと考えていませんか?スパイラルの「Webフォーム作成ツール」を活用すれば、問い合わせフォームのかんたん作成はもちろん、分散しやすい個人情報の一元管理が可能です。
Webフォーム作成ツールの主な特長
- アンケート、予約、キャンペーン応募、出願など幅広い用途に対応
- プログラミング不要でPC・スマホ対応フォームを作成可能
- HTML・JavaScript・PHPを用いてデザインや動的制御を追加可能
- 不正登録防止など安心のセキュリティ機能を搭載
金融・製造・小売・学校・飲食・官公庁など、多くの企業に選ばれています。
まとめ
問い合わせ対応の効率化は、単なる業務負担の軽減にとどまらず、顧客満足度の向上や従業員の働きやすさの改善にも直結します。
特に問い合わせ件数が増加している企業や、人手不足で対応が追いつかない中小企業は、まずは低コストで始められるFAQやテンプレート整備から着手し、段階的にツール導入を検討するのがおすすめです。まずは、無料で利用できる効率化ツールや導入事例の資料をチェックして、最適な方法を見つけましょう。