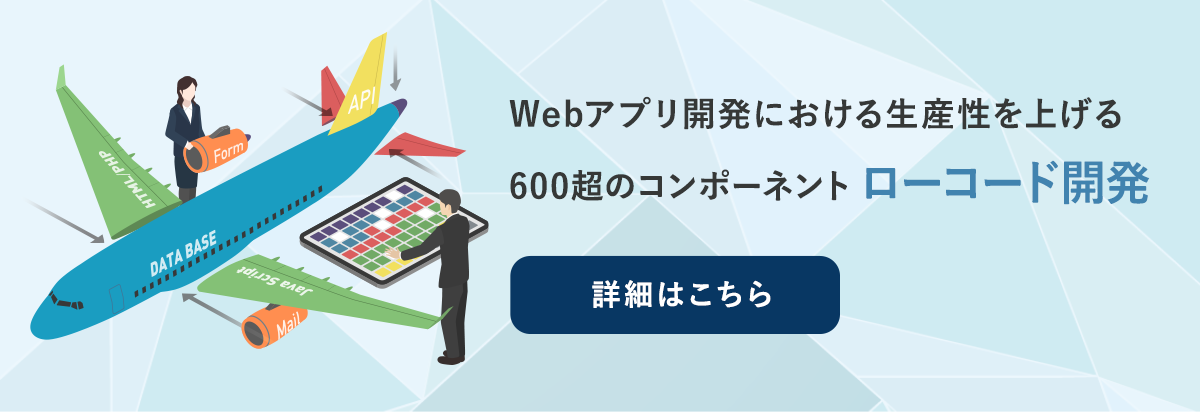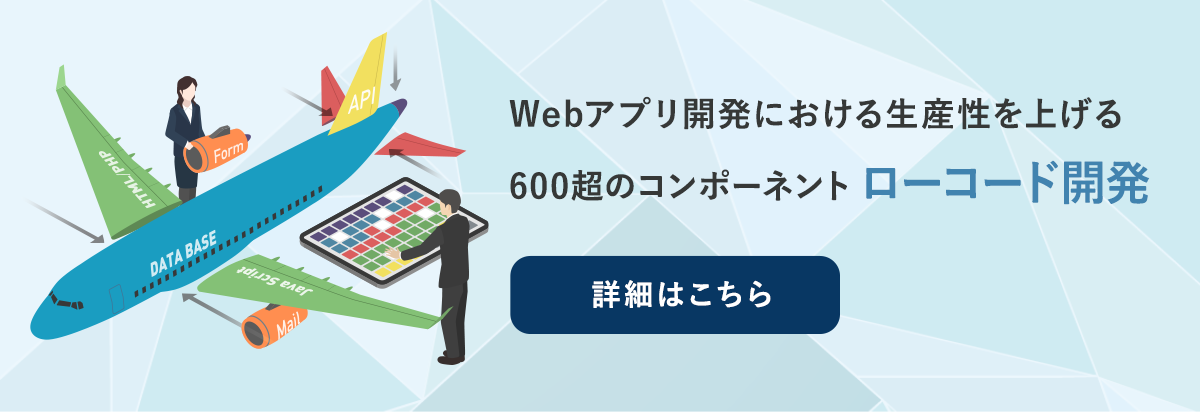ローコード開発の記事
ARTICLEローコード開発のセキュリティは不安?非エンジニアでもできる対策も
ローコード・ノーコード開発は効率的な反面、セキュリティ面で不安を感じることもあるのではないでしょうか。特に非エンジニアである場合、専門的な知識がないとより一層、不安に感じてしまうかもしれません。そこで、この記事では認証制度やセキュリティ要素、非エンジニアでも可能な具体的な対策を解説します。
目次
ローコード・ノーコード開発とは

ローコード・ノーコード(LCNC)開発とは、ドラッグ・アンド・ドロップなどの直感的な操作や最低限のコーディングだけで業務アプリの開発を行う手法です。
短期間で開発できることや、高度な専門知識を求められないことから利用する企業が増えていますが、ここではそんなローコード・ノーコード開発が活用されている特徴や背景を詳しく解説します。
関連記事:ローコード開発とは?特徴・メリット/デメリットと導入前のチェックポイントを解説
ローコード・ノーコード開発の特徴
ローコード・ノーコード開発は、従来のソフトウェア開発に比べてコードの記述量を大幅に削減できる手法です。
特に、テンプレートの活用やドラッグ・アンド・ドロップ操作などでアプリ構築ができる点が特徴です。
エンジニアでなくても容易な操作で開発できるため、仕様変更や追加開発にも柔軟に対応しやすく、求めている機能によっては短期間での作成も可能です。
このように、開発のハードルを下げながらも一定の品質を保てる点が、従来の開発手法と比較した際の大きな強みと言えるでしょう。
ローコード・ノーコード開発が活用されている背景
ローコード・ノーコード開発が注目を集めている背景には、急速に変化する市場に対する柔軟な対応が求められている点が挙げられます。
顧客ニーズや業務プロセスの変化へ迅速に対応するためには、従来のような長期間を要する開発手法では対応しきれない場合もあるでしょう。
特に、現場主導の開発や業務の内製化の必要性はより一層増しています。
また、エンジニア不足の深刻化も無視できません。
コスト・時間の面から専門的な知識を持った技術職の確保が難しくなってくる中で、非エンジニアであっても自社に必要なアプリの開発が可能なローコード・ノーコード開発手法は有効な選択肢になっているのです。
ローコード・ノーコード開発にセキュリティ強化が必要な理由

ローコード・ノーコード開発は利便性の高さゆえに活躍の場を急速に広げています。
ただし、開発方法によってはリスクが生じてしまうこともあります。
そこで、ここではローコード・ノーコード開発にセキュリティ強化が必要な理由を解説します。
セキュリティ基準が曖昧になってしまう可能性がある
ローコード・ノーコード開発では開発の利便性が高い反面、誰がどのような意図で作成したのか判別しにくく属人化してしまうことも珍しくありません。
特に、ロジックやデータ連携が複雑に絡み合い、第三者には処理の流れが全く追えない「ブラックボックス」のような状態になってしまうことがあります。
また、社内で定めていたはずのセキュリティ基準が開発したアプリごとに異なり、統一性を損なってしまうことがあります。
開発部門を介さないと全社的な影響を及ぼしてしまうリスクも無視できません。
適切な手順を踏まない「セキュリティ承認」や「開発プロセス」が含まれると、企業全体のガバナンスへ影響を及ぼしてしまう可能性があるためです。
そのため、ローコード・ノーコード開発であっても、通常のアプリ開発と変わらず、ガバナンスの周知・強化は欠かせません。
「野良アプリ」が出現する可能性がある
ローコード・ノーコード開発の魅力はなんといっても手軽さですが、反面、IT部門の管轄外でアプリが作成・運用される「野良アプリ」と呼ばれるアプリが発生しやすいという側面も存在します。
こうしたアプリは正式な管理体系からは外れており、ログの取得やバックアップが万全に行われないこともあります。
そのため、万が一不正アクセスや情報漏洩が起きてしまった場合に、察知が遅れる場合があります。
また、野良アプリを現場担当者が独自に作成・運用しているケースでは、属人化しやすい傾向にあります。
例えば「担当者の退職や異動によって、脆弱性の引き継ぎが不十分になることでセキュリティホールを見過ごしてしまう」といった事態も起きかねません。
テンプレートや自動生成ツールを用いることでブラックボックス化しやすい
ローコード・ノーコード開発では、テンプレートや自動生成AIによるコードを多用しすぎると、作成者自身が裏側の処理を把握できていない場合があります。
特に、一般的なアプリ開発では作成しているはずの設計書やドキュメントが明示的に残らないまま運用されているケースもあり、開発後の修正を行う際の障害となる場合や欠陥を見過ごしてしまう原因になることがあります。
また、便利なツールへ依存しすぎることで、仕組みや危険性を「調べない文化」が定着してしまうことも潜在的なセキュリティリスクになり得ます。
例えば、細かな設計の意図やセキュリティ上の注意点が置き去りにされることで、本来エンジニアであれば避けることが可能であろう初歩的なミスを見過ごしてしまうことがあります。
ローコード・ノーコード開発でも意識すべき情報セキュリティの3要素「CIA」とは

情報資産を守るためには「CIA」と呼ばれる3つの視点を意識することが重要とされています。
ローコード・ノーコード開発においても、この要素は重要です。
CIAはそれぞれ「機密性(Confidentiality)」「完全性(Integrity)」「可用性(Availability)」の頭文字を取ったもので、具体的な特徴は以下です。
| セキュリティ要素 | 機密性(Confidentiality) | 完全性(Integrity) | 可用性(Availability) |
| 特徴 | 許可のある人だけがアクセスできる状態を保つこと | 情報が正確で改ざんや誤変更ができない状態を保つこと | 必要なときに必要な情報へ問題なくアクセスできること |
ここではそれぞれの要素や、具体的に効果的な対策を詳しく解説します。
機密性(Confidentiality)
機密性(Confidentiality)とは、適切な権限を持つユーザーのみがアクセスできる状態を保つことです。
機密性の確保が十分でないと、顧客情報や営業秘密といった重要な情報が外部に漏れてしまい、企業の競争力低下や社会的信用の失墜といった深刻なリスクを誘発しかねません。
特に、ステークホルダーの個人情報や上場予定の未公開情報など、取り扱いに慎重を要するデータには高い機密性が求められます。
また、情報アクセスの制御を意識する上では、「特権ID」の扱いも重要です。
システム内で高い権限を与えられている特権IDは、操作ミスや不正利用をされると影響を及ぼす範囲が大きいことが特徴です。
そのため、ローコード・ノーコード開発であっても「厳格な監視」「ログ取得」「利用制限」といった一般的な対策が重要と言えるでしょう。
完全性(Integrity)
完全性(Integrity)とは、扱う情報やデータが正確かつ完全であり、改ざんや破損の生じていない状態を維持することです。
完全性を失うと業務判断に誤りが生じることや、法的責任を問われてしまうリスクが高まってしまうこともあります。
完全性の求められる情報として、以下が挙げられます。
- 財務諸表や帳簿類などの会計情報
- 医療記録
- 契約書や申請書類などの電子帳簿保存法に関連する記録
- 業務基幹データ
完全性を確保するためには、「デジタル署名」や「データ検証」、「ログ管理」や「改ざん検知システムの導入」が効果的です。
可用性(Availability)
可用性(Availability)とは、必要なデータやサービスに確実にアクセスできる状態を維持することです。
可用性の欠如は業務の停止や遅延につながるだけでなく、顧客対応の不備や社会的信用の低下といった企業のブランドイメージにも影響が波及することもあります。
特に災害時における「安否確認情報」や「緊急連絡網」、「業務マニュアル」などの可用性は、近年、加速しているDXにおいて重要視されやすいレジリエンスにも寄与します。
また、オンライン予約や在庫管理などの「業務システム」、社内チャットなどの「リアルタイムの情報共有ツール」は業務プロセスの改善にも役立ちます。
高い可用性を維持するためには、複数のディスクにデータを分散・冗長化して保存する「RAIDの活用」や「UPS(無停電電源装置)」により停電時でもシステムへ継続的に電力供給することが効果的です。
これらはローコード・ノーコード開発の場合であっても開発方法に依存しないため効果的です。
CIAだけじゃない?ローコード・ノーコード開発に重要な情報セキュリティ4要素とは

高いセキュリティを維持するためにはCIA以外の要素にも焦点が当たることがあります。
そこで、ここではCIAと合わせて重要視される以下の4つの要素と、ローコード・ノーコード開発において注意すべき事項についても解説します。
| セキュリティ要素 | 真正性(Authenticity) | 信頼性(Reliability) | 責任追跡性(Accountability) | 否認防止(Non‑repudiation) |
| 特徴 | 情報や利用者が正当であることを保証すること | システムやデータが安定して正しく動作すること | 誰がいつ何を行ったかを追跡・証明できること | 特定の行為を行った者を後から否定できないようにすること |
真正性(Authenticity)
真正性(Authenticity)とは、情報や利用者が正当・正規のものであることを確認・保証することです。
真正性の欠如は、なりすましや改ざんによる不正アクセスといった事態につながりかねません。
真正性の向上には、システムにログインするユーザーが正しい本人であることを認証する仕組みや、送受信するデータが信頼できる送信元から発せられたものかを確認する手法が欠かせません。
具体的には、パスワードだけでなく「多要素認証(MFA)」や「ワンタイムパスワード」「デジタル証明書の利用」などの対策が有効です。
ローコード・ノーコード開発でAPIなどによる外部連携やユーザー管理を行う場合は、真正性を確保する設定や仕組みを適切に導入することが重要と言えるでしょう。
信頼性(Reliability)
信頼性(Reliability)とは、システムやデータが意図した通りに正しく動作し、安定した状態を維持することです。
信頼性を損なうと、システムの不具合や予期せぬエラーによって業務が滞ってしまい、業務品質や安全性に深刻な影響を及ぼす可能性が高まる原因になります。
特に、業務基幹システムや顧客対応システムの障害は、組織の信用失墜や損害につながる恐れがあります。
そのため、「十分な負荷試験」「冗長化構成」「外部サービス連携部分の安定性検証」など、動作の確実性を担保する取り組みが欠かせません。
ローコード・ノーコード開発では、テンプレートやプラグインに依存しすぎず、バージョン管理や更新状況を定期的に確認することで、信頼性を高めることが求められます。
責任追跡性(Accountability)
責任追跡性(Accountability)とは、誰がいつ、どのような操作を行ったのかを記録し、必要に応じて追跡できる状態を維持することです。
この要素が不十分だとトラブルや不正が発生した際に原因を特定できず、適切な対処や説明責任を果たせなくなります。
例えば、重要なデータの削除や権限変更が行われた場合、実行したユーザーのIDや実行された時間などの情報が不明だと業務に大きな支障をきたすことがあります。
そのため、「ログの取得・保管」「操作履歴の可視化」「アクセス権限の適正管理」などが重要です。
簡便な構造であることの多いローコード・ノーコード開発であっても、操作ログを自動で記録する仕組みやバージョン管理の導入によって責任追跡性を確保することが重要です。
否認防止(Non‑repudiation)
否認防止(Non‑repudiation)は、特定のアクションや取引の実行ユーザーが後から「自分は行っていない」と否定できないようにする仕組みのことです。
この要素が不十分だと、トラブルや紛争が生じた際に行為を証明できなくなってしまいます。
そのため、被害を受けた組織や関係者にとって不利な状況となる可能性があります。
例えば、重要な承認手続きや取引データの送受信において、当事者の署名や操作証跡が残っていない場合、責任の所在を立証できず問題解決が難しくなることがあります。
具体的には、「デジタル署名」や「タイムスタンプ」「電子証明書の活用」「詳細な操作ログの保管」といった対策が有効です。
現場で開発・運用されることの多いローコード・ノーコード開発では、ワークフロー承認や外部送信機能を備えたアプリで、重要な操作や取引の実行を明確に証明できるように維持することが求められます。
非エンジニアでもできる!ローコード・ノーコード開発のセキュリティ対策

ローコード・ノーコード開発は本来、気軽に開発が可能であることが特徴です。
ただし、セキュリティ向上において専門知識が多く、戸惑ってしまうこともあるのではないでしょうか。
そこで、ここではエンジニアをはじめ、専門知識を有している人でなくても可能なローコード・ノーコード開発におけるセキュリティ対策を解説します。
権限設定を「最小限」にする
ユーザーごとに「閲覧のみ」「入力のみ」「編集・削除も可能」といった操作範囲を細かく制限し、本当に必要な作業だけを許可することが重要です。
特に、不要な権限の誤った付与や、意図しない情報漏洩・改ざんといったリスクを低減するためにも重要です。
このような取り組みは「最小権限の原則」と呼ばれ、情報の機密性を保ちながら責任追跡性も担保することができます。
「ID連携」や「2段階認証」の採用
パスワードのみの認証では、不正アクセスのリスクを完全に排除することは難しいのが現状です。
そのため、ログイン管理にはより堅牢で安全な対策が求められます。
特に、「シングルサインオン(SSO)」や「ID連携機能」を用いることで、複数のアカウント管理を一元的に管理することが可能になることで、利便性だけでなく認証強度向上に寄与します。
また、SMS認証やワンタイムパスワードなどの2段階認証の併用も効果的です。
このような対策で、万が一パスワードが流出してしまっても不正ログインを防ぎやすくなります。
これらの対策はローコード・ノーコード開発でも容易に設定でき、非エンジニアでも取り組める有効な施策です。
テンプレートやプラグインの信頼性を確認する
テンプレートやプラグインを導入する際は、見た目や機能の便利さだけで判断しないようにしましょう。
開発元の信頼性や利用実績を確認することが重要です。
特に、利用しているサービス以外の外部ベンダーが提供しているアドオンやコードスニペットにセキュリティ上の脆弱性や不具合が潜んでいる場合もあります。
導入前にレビューや更新履歴などの情報も併せて確認し、公式のサポート体制が整っているかをチェックすることで安心して利用できるようになるでしょう。
SPIRAL®の「ローコード開発ツール」なら必要な機能を自由に追加できる上に、メンテナンスやセキュリティ対策も全てお任せ可能!

ローコード開発を行う際のセキュリティ対策に不安を感じているなら、SPIRAL®の「ローコード開発ツール」がおすすめです。「ローコード開発ツール」には以下のようなローコード開発のセキュリティ対策にぴったりな特徴が存在します。
1. 柔軟なカスタマイズが可能なフォーム作成機能
「フォーム作成機能」は管理画面のUI上で容易に編集が可能で、HTML・CSSの編集はもちろん、JSやPHPを用いることもできるため、自由自在なカスタマイズが可能です。
2. 高度なログイン認証機能とセキュリティ対策
ID・パスワードによる認証機能を提供し、ログイン試行回数に応じたログインロックの実施やパスワードの強度設定等もかんたんに設定できます。セキュリティ対策も施されているため、専門知識がない方でも安心してご利用いただけます。
3. 脆弱性対策済みだから集中してアプリ開発が可能
SPIRAL®は、開発プラットフォームとしてのセキュリティ対策はもちろん、定期的に外部の脆弱性診断を受けており、サーバーの保守やセキュリティ対策も不要なため開発に専念することができます。
まとめ
ローコード・ノーコード開発(LCNC)は、非エンジニアでも直感的な操作で業務アプリを開発できる手法として注目されています。
一方で、セキュリティ対策が不十分なまま利用範囲が拡大すると、「野良アプリの発生」や「ブラックボックス化」、「セキュリティ基準の不均一化」といったリスクを誘引する可能性があります。
そのため、CIA(三要素:機密性・完全性・可用性)や情報セキュリティ7要素を意識し、運用・管理することが重要です。
ローコード・ノーコード開発を活用する際は、利便性だけでなく「セキュリティを組み込んだ運用」が成功の鍵となるでしょう。