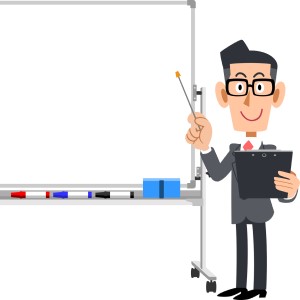匿名型通報・相談窓口システムの記事
ARTICLE内部告発・内部通報とは?制度の意義とメリット、過去の事例を解説!
この記事では、内部告発と内部通報の意義と相違点をわかりやすく解説します。企業による不正や不祥事が相次ぐ中、内部通報制度の整備は自社の社会的信頼性を高めるために重要です。過去に訴訟となった事例もご紹介していますのでぜひ参考にしてください。
目次
内部告発と内部通報の定義と相違点

はじめに、内部告発と内部通報の定義について解説するとともに、相違点をご紹介していきます。
内部告発とは
内部告発とは、従業員が社内で不正行為や法令違反が行われているのを発見した場合に、監督官庁・報道機関・SNSなど会社の外部に告発することです。
内部告発がなされた場合、社内で慎重に対応する時間的な余裕はなく、告発内容が会社の外部に急速に広まってしまうため、自浄作用のない企業として社会的な信頼を失ってしまうリスクがあります。
特に、このあとご紹介する内部通報の制度を導入していない、あるいは有効に機能していない企業では、従業員は内部告発の手段を取るしかないため注意が必要です。
内部通報とは
内部通報は、社内で行われている不正行為や法令違反について、発見した従業員が会社の設置した通報窓口に通報することをいいます。通報窓口としては、自社の管理部門内に設置する場合、弁護士事務所に委託する場合、双方を併設する場合などがあります。
内部通報では、社内および委託する弁護士事務所とで一次対応、対策の検討が可能で、自社内部での問題解決が期待できます。
したがって、内部告発がなされた場合よりも企業の受けるダメージの抑制につながるといえるでしょう。
内部告発と内部通報の相違点
このように、内部告発と内部通報はいずれも社内の不正行為や法令違反を正すために、従業員が取りうる通報の手段という点で共通していますが、通報先が社内か社外かという点で大きく異なります。
また、公益通報者保護法で保護されるかどうかという点でも内部告発と内部通報には違いがあります。
公益通報者保護法は、通報したことで従業員が解雇や降格などの不利益な取り扱いを受けないように、通報者を守る法律ですが、内部通報者には適用されるのに対して、内部告発者には原則適用されません。
従業員にとっては、内部告発は大きなリスクを伴う手段といえます。
内部通報制度の意義と目的

ここからは、内部通報制度の意義と目的について解説していきます。
内部通報制度とは
内部通報制度とは、社内の不正行為や法令違反を発見した従業員からの通報や相談を受け付け、通報者を厳格に保護しつつ、調査・是正・是正後のモニタリングを行う仕組みです。
公益通報者保護法では、常時使用する従業員の数(パートタイム労働者、契約社員、派遣労働者等も含む)が300人を超える企業について、内部通報制度の整備を義務付けています。
一方、従業員の数が300人以下の企業は、内部通報制度の整備に努めるよう要請にとどまっていますが、従業員数に関わらず内部通報制度を整備していない場合、消費者庁の行政措置の対象となり、企業名が公表される場合があることを認識しておきましょう。
内部通報制度では、通報対応責任者・通報窓口・通報対応従事者を定めるとともに、内部規定や対応マニュアルなどの整備が必要です。
内部通報制度の目的
内部通報制度は、社内の不正行為や法令違反を早期に発見・是正することで、健全な企業経営を推進し企業価値を高めることを目的としています。
近年、企業規模を問わず、粉飾決算、試験データ改ざん、産地偽装、情報漏えい、横領などさまざまな不正が発覚し、社会的信用を失う企業が後を絶ちません。SNSが普及したことで、企業イメージにマイナスとなる情報は急速に拡散され、経営に与える影響も大きくなっています。
企業が将来にわたって存続・成長を続け、従業員が安心して勤務するためにも、内部通報制度は重要な役割を果たすといえます。
内部通報制度を導入するメリット

内部通報制度を導入するメリットを「不正の早期発見」、「社会的な信頼性の確保」の2つの視点から解説します。
不正の早期発見
内部通報制度を導入すると、社内の不正行為を早期に発見することで被害の拡大を抑制する効果が期待できます。
実際に、消費者庁が公表している「令和5年度民間事業者等における内部通報制度の実態調査報告書」では、不正発見の端緒として、「内部通報 68.4%」、「上司による日常的な業務のチェック、従業員等からの業務報告等 44.8%」、「内部監査 41.9%」となっており、内部通報制度が不正発見に大きな役割を果たしているのがわかります。
不正発見のきっかけとして多いものを尋ねた。 「従業員等からの内部通報(通報受付窓口や管理職等への通報)」が最も高く 68.4%、次いで「上司による日常的な業務のチェック、従業員等からの業務報告等」44.8%、「内部監査(自社・自団体の監査部門による監査)」41.9%と続く結果となっている。
出典:令和5年度民間事業者等における内部通報制度の実態調査報告書
近年、上司によるチェックや内部監査で発見できない不正が増加しており、内部通報制度の重要性は今後ますます高まっていくでしょう。
社会的な信頼性の確保
内部通報制度の導入は、社会的な信頼性を確保するのにも大変有効です。不正行為の抑止効果に加え、万が一、不正行為があった場合でも早期発見・解決の可能性が高く、自浄作用の働く企業と評価されるでしょう。
また、通報を理由として、解雇・降格・減給などの不利益な取り扱いをしないと示すことで、従業員が安心して勤務できる職場環境を提供できます。
したがって、内部通報制度を整備することで、取引先・従業員・株主などのさまざまな利害関係者からの信頼獲得が期待できます。
公益通報者保護法で保護される公益通報(内部通報)の条件

公益通報者保護法が適用され、通報者が保護されるためには、「誰が」「どのような事象を」「どこに」通報するかについて、いくつかの条件がありますのでご紹介します。
公益通報(内部通報)を行える者
公益通報(内部通報)を行える者は、現在企業に勤務し賃金を得ている正社員・公務員・パートタイマー・アルバイト・派遣労働者、取締役・監査役などの役員のほかに、退職から1年以内の退職者、派遣労働の終了から1年以内の派遣労働者も含まれます。また、契約に基づき事業を行っているときは、その事業に従事する取引先事業者の労働者も対象です。
なお、2025年の公益通報者保護法改正で、公益通報(内部通報)を行える者として、事業者と業務委託関係にあるフリーランス、業務委託が終了して1年以内のフリーランスが追加されました。
公益通報(内部通報)の対象となる事象
公益通報(内部通報)の対象となる事象は、通報者の勤務先に関するものであり、かつ、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」(505本)に規定されている犯罪行為、過料対象行為、行政指導や行政処分となる行為です。
具体的には、有害物質を含む飲食品の販売、会社の金品の横領、粉飾決算、残業代の不払い、暴力や脅迫行為、無資格者による検査、許認可を取得していない営業、産地偽装などが挙げられます。
公益通報(内部通報)先
公益通報(内部通報)先には、勤務先・監督官公庁・報道機関の3つがあり、保護される要件がそれぞれ異なります。
勤務先への通報の場合には、勤務先が設置する社内の内部通報窓口、勤務先が委託した法律事務所などに通報することになりますが、保護の対象となるには、通報対象事実が発生している、またはまさに発生しようとしていると思われることが必要です。
監督官公庁などの行政機関に通報する場合は、通報対象事実が発生し、またはまさに発生しようとしていると信ずるに足りる相当の理由(証拠や関係者の供述など)に加え、通報者の住所・氏名が要求されます。
報道機関に通報する場合、通報対象事実が発生し、またはまさに発生しようとしていると信ずるに足りる相当の理由(証拠や関係者の供述など)があり、かつ通報により解雇される可能性が高い・証拠隠滅の可能性が高いなど相当の理由があることが必要です。
公益通報(内部通報)の方法
面談・電話・FAX・メール・書面郵送など勤務先・監督官公庁・報道機関の各通報先でそれぞれ通報方法が定められています。
内部告発の具体的事例3つ

ここでは、内部告発の具体的事例を3つご紹介します。
油圧機器メーカーの検査データ改ざん、不適合製品の出荷
2018年、油圧機器メーカーで免震装置の検査データを改ざん、不適合製品を出荷していたことが公表されました。子会社の検査員が内部告発し、2カ月間の社内調査を経て、少なくとも15年間にわたって改ざんが行われていたことが明らかになりました。同社は、改ざんの疑いのある免震・制振装置を2年で交換完了する計画ですが、国交省は免震装置メーカー88社に対して、改ざん有無の一斉調査を行うことを発表しています。
引っ越し業者による過大請求
2018年、大手宅配業者の子会社である引っ越し業者で、サービスを提供した約8割の企業に対して過大請求を行っていたことが内部告発により判明しました。2011年にも同様の内部告発がありましたが、全国的な問題とは受け止めず、個別の調査の後、過大請求分を返金していました。
同社は、国土交通省に報告書と再発防止策を提出し、これを受け、国土交通省は同社に事業改善命令を出すとともに、過大請求のあった123事業所に車両の使用停止の行政処分を行い、支店長の指示が確認されるなど悪質な4支店については最長7日間の事業停止処分としました。
大手製紙メーカーで不適切会計に関する内部告発を行った従業員を懲戒解雇
2012年、大手製紙メーカーの従業員が、経営陣と対立する当時の顧問に不適切会計に関する内部告発を行いました。従業員は就業規則違反で降格、子会社への出向を拒んだところ、2013年に懲戒解雇されました。
判決では、告発内容を裏付ける客観的資料が乏しく、経営陣を失脚に追い込むためと判断され、降格処分は不当とはいえないとされました。
ただし、子会社への出向命令については、出向命令権の乱用に当たるとして、拒否を理由とする解雇を無効としています。
内部通報の具体的事例2つ

ここからは、内部通報の具体的事例を2つご紹介していきます。
精密機器メーカーで通報内容の無断漏洩
2007年、精密機器メーカーに勤務する従業員が上司の不正行為をコンプライアンス室に内部通報しました。ここで、コンプライアンス室から従業員へ返信メールをする際に宛先に通報対象者である上司を含めたため、通報者および通報内容が漏えいしました。その後、従業員には配転命令が出され、異動をしています。
一審判決では従業員が敗訴、二審判決では配転命令が無効で、会社側に賠償が命じられる逆転勝訴となりました。
千葉県の医療機関が通報者を報復として担当業務から外す
2010年、千葉県の医療機関に勤務する麻酔科医が、研修が厚生労働省のガイドラインに沿って実施されていないことについて、センター長に内部通報を行いました。
しかし、対応が不十分なまま、これまでの担当業務から外されるとともに、通勤の難しい遠隔地への異動を命じられたため、やむを得ず退職しました。
麻酔科医の起こした訴訟では、医療機関側の報復を目的とした不利益な取り扱いと認定され、慰謝料30万円の支払いが命じられました。
匿名型通報・相談窓口システムのご紹介

当社は、自社で開発・提供するクラウドサービス「SPIRAL®」を基盤として、「匿名型通報・相談窓口システム」を提供しています。
完全匿名性で1対1形式のため安心して相談できるのに加え、相談者も担当者もかんたん操作でご利用いただけます。
ハラスメント相談、コンプライアンス通報、育児介護休業法に基づく相談、女性特有の相談(フェムケア、健康経営)などさまざまなシーンでご活用いただけますので、さらに詳しく知りたいという方はぜひ以下URLをご覧ください。
サービスの詳細については「匿名型通報・相談窓口システム」のページをご覧いただくか、サービス導入をご検討中の方はこちらからぜひお問い合わせ下さい。
まとめ
この記事では、内部告発と内部通報の定義と相違点、内部通報制度の意義と目的・導入メリット、内部告発・内部通報の具体的な事例などについて解説しました。
内部告発と内部通報はどちらも社内の不正行為や法令違反を正すために、従業員が取りうる通報の手段です。
しかし、内部告発の場合にはいきなり情報が外部に出てしまうため対応が難しく、かつ会社に与えるダメージも大きなものとなります。
内部通報制度を整備することで、社内の不正を早期に発見できるとともに、内部告発が行われる機会の抑制も期待できます。
従業員・取引先・株主などさまざまな利害関係者からの信頼・評価も高まるため、当記事を参考にぜひ自社の内部通報制度構築にお役立てください。