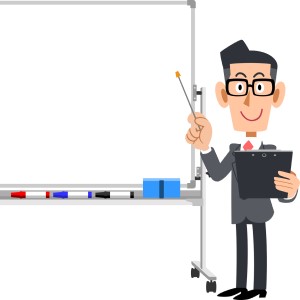匿名型通報・相談窓口システムの記事
ARTICLE内部通報制度の導入方法とは?企業が守るべき手順と成功のポイント
公益通報者保護法に対応するために、内部通報制度を早急に導入したいと考えていないでしょうか。しかし、具体的な導入手順がわからずお困りの人もいるはずです。この記事では、内部通報制度の失敗しない導入方法を、よくある失敗例や注意点も含めてわかりやすく解説します。
目次
なぜ今、内部通報制度の導入が求められているのか?

近年、企業の不祥事の発覚が相次ぎ、コンプライアンス体制の強化が社会的に強く求められています。その中心にあるのが「内部通報制度」です。
特に、公益通報者保護法の改正を受け、従業員や取引先が安心して不正を報告できる仕組みづくりが急務となっています。そこでまずは、内部通報制度の導入が求められる理由をわかりやすく解説します。
【理由1】改正公益通報者保護法により制度導入が必要に
企業が内部通報制度を導入すべき一番の理由は、公益通報者保護法の改正です。特に、2022年6月に施行された改正法では、従業員300人超の事業者に対し「内部通報体制の整備」が義務化されました。
この改正では、内部通報の受付や調査を行う担当者に守秘義務が課され、違反した場合には罰則が科されるなど、通報者が安心して声を上げられる実効性のある仕組みづくりが求められています。体制を整備しない場合、行政による助言や指導、勧告の対象となるため、法令遵守の観点から対応が不可欠です。
このような理由から、企業は早期に内部通報制度を導入しなければならないのです。
【理由2】内部通報制度が企業リスクを減らす
内部通報制度には導入すべき根本的な理由もあります。それが企業リスクの早期発見と抑止です。
たとえば、内部通報制度を導入することにより、次のようなリスクを低減できます。
- 会計不正や贈収賄などの重大不祥事を早期に把握
- セクハラ・パワハラといった職場トラブルの拡大を防止
- 行政処分や株主訴訟などによる信頼失墜リスクを軽減
つまり、ニュースでも取り上げられている不祥事を早期(未然)に解決できると言えるでしょう。そのため、内部通報制度は単なる法令対応ではなく、企業の持続的な成長を支えるリスクマネジメントとして欠かせない対策です。
内部通報制度の基本構成

内部通報制度を導入する際には、単に通報窓口を置くだけでなく、受付から調査、再発防止まで一貫した体制を整えることが重要です。
ここでは、通報の対象行為や制度全体の流れを整理します。
内部通報の対象となる行為事例
内部通報制度で対象となるのは、法律違反行為に限りません。企業の倫理規定や就業規則に反する行為も広く含まれるのが一般的です。
公益通報者保護法で定められた「通報対象事実」に加え、企業が自主的に設定するコンプライアンス違反など、具体的には以下のような行為が対象となります。
- 会計不正や脱税、架空請求などの経理上の不正
- 贈収賄、談合、カルテルなど公正取引に反する行為
- 個人情報保護法違反、情報漏えい
- 環境法令や労働安全衛生法などの違反行為
- セクハラ・パワハラ・マタハラなどの各種ハラスメント
企業によって細部は異なりますが、これらを網羅し通報してよいケースを一覧化することで従業員は安心して通報でき、組織はリスクを早期に察知できます。
内部通報の全体の流れ(通報者・窓口・調査・再発防止まで)
内部告発は、主に次の流れで実施されます。
| フェーズ | 内容 | 関係者 |
| 通報 | 電話・メール・匿名フォームで通報する | 従業員・取引先 |
| 受付 | 内容を記録し、秘密保持を徹底する | 通報窓口(内部/外部) |
| 調査 | 関係者についてヒアリング・証拠収集する | コンプライアンス部門・第三者委員会 |
| 是正 | 違反行為の是正・処分を検討する | 経営層・人事部 |
| 再発防止 | 改善策を実施する、また再発防止研修を行う | 経営層・教育担当 |
制度を設ける際には、この流れを文書化し、従業員に周知することが欠かせません。
内部通報制度の失敗しない導入ステップ【5工程】
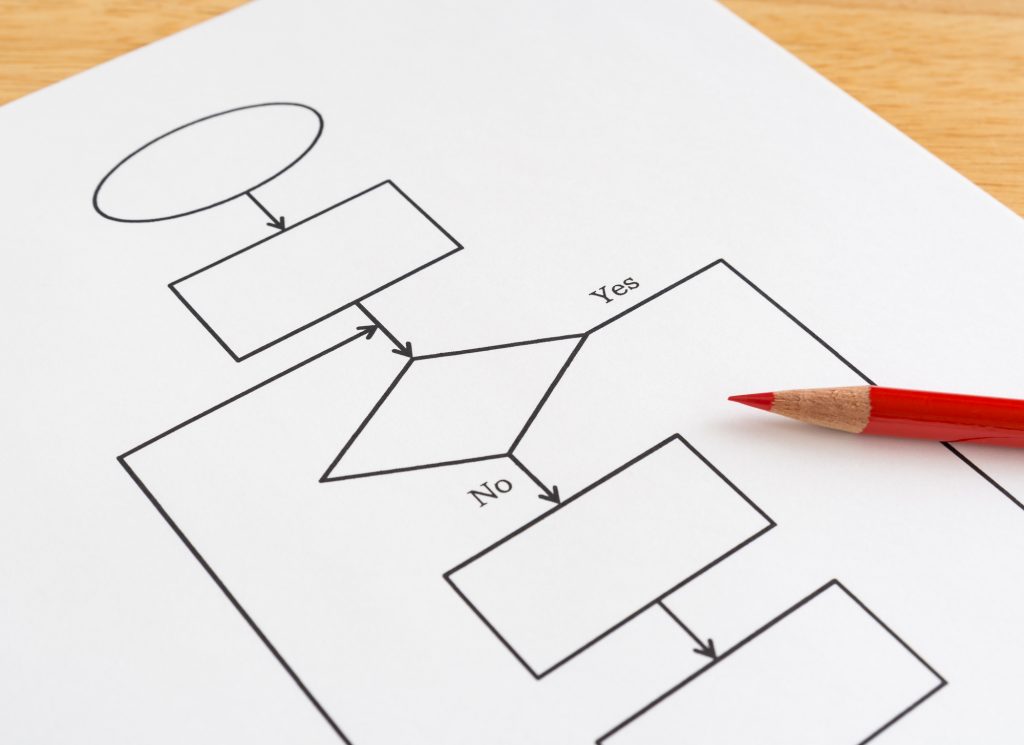
内部通報制度を効果的に機能させるためには、従業員が安心して利用できる環境を整備することが重要です。
ここでは、実務で役立つ5つの導入工程を解説します。
【ステップ1】導入目的と対象範囲を明確にする
まず、制度を形骸化させないために「目的」「対象範囲」を明確化することが重要です。たとえば、以下のように整理していきましょう。
- 目的|不正行為の早期発見・企業倫理の確立
- 対象範囲|従業員・役員・取引先など通報可能な関係者を定義
- 対象行為|会計不正・ハラスメント・法令違反等
目的と範囲を明確にできれば、従業員が安心して制度を利用できるようになります。また、経営側も調査リソースを適切に配分しやすくなるため、ファーストステップとして実施しましょう。
【ステップ2】通報窓口を設置する
通報窓口は制度の「入口」であるため、信頼性の担保として複数のルートを設けるのがベストです。
複数経路を確保すれば、通報者が社内にバレる心配を減らしつつ相談しやすくなります。
【ステップ3】規程・マニュアルを整備する
設置する窓口の種類が決まったら、次のような規程やマニュアルを整備しましょう。
- 内部通報規程(対象範囲・窓口・手続き)
- 調査マニュアル(調査責任者・手順・報告期限)
- 秘密保持に関する規程
こうした文書化は、行政調査や訴訟時の防御にも有効です。なお、通報受付に関する規定やマニュアルだけではなく、調査、報告など、発生する動きをすべて体系化することが大切です。
【ステップ4】通報者を保護する仕組みを構築する
制度が実効性を持つかどうかは、通報者が安心して利用できる「保護の仕組み」にかかっています。
公益通報者保護法では、通報したことを理由とする解雇や降格などの「不利益な取り扱い」を明確に禁止しています。企業がこのルールに違反した場合、行政指導の対象となるほか、通報者から損害賠償を求められる可能性があります。
通報者を守るために、具体的には以下のような仕組みを規程に明記し、徹底することが不可欠です。
- 通報者情報の徹底した秘匿
通報者を特定できる情報の共有範囲を必要最小限に限定し、担当者には厳格な守秘義務を課します。(守秘義務違反には刑事罰が科されます) - 報復行為の禁止と罰則の明記
通報者に対するいかなる報復行為(嫌がらせ、不利益な人事評価など)も禁止することを規程で明確にし、違反者には懲戒処分を科すことを周知します。 - 匿名での通報を可能にする
身元を明かさずに通報できる匿名チャネル(Webフォームなど)を設けることで、通報の心理的ハードルを下げます。
これらの保護体制を整備し、従業員に明確に伝えることで、制度への信頼が高まり、利用促進につながります。
【ステップ5】従業員への周知と教育研修を実施する
最後に重要なのが「従業員教育」です。
どんなに良い制度が存在していても、その存在が知られていなければ利用されません。以下のような方法で浸透を図るのがおすすめです。
- 入社時オリエンテーションで制度を説明する
- 定期的なeラーニングや集合研修を実施する
- ポスター・イントラ掲示板で啓発する
- 事例ベースのケーススタディ演習を実施する
従業員の理解と信頼を得て初めて、制度は実効性を発揮します。ただ制度をつくるのではなく、従業員への周知を徹底しましょう。
内部通報制度を導入する際の注意点とよくある失敗例

社内で整備した内部通報制度に不備があると、通報が寄せられず形骸化したり、逆に企業リスクを増大させたりする恐れがあります。
ここでは、特に注意すべき3つのポイントを紹介します。
【注意点1】通報者が保護されない制度設計になっている
通報者の保護をせずに制度を運用しようとすると、従業員に次のような不安を与えて「使われない仕組み」になってしまいます。
- 通報者の匿名性が守られず身バレする
- 上司に筒抜けになり、報復を受けてしまう恐れがある
- 通報後に異動・評価低下などの不利益を受ける
公益通報者保護法では、通報者に対する解雇や降格などの不利益取り扱いを禁止していますが、現場レベルで徹底されていないケースも考えられます。
そのため、現場レベルでの徹底が甘いと利用率は急落するため、正しく整備することからスタートしましょう。
【注意点2】通報後の対応フローが不透明・属人的になる
制度を設けても、対応フローが曖昧だと従業員は安心して通報できません。
たとえば、調査責任者が固定されず属人的に処理されるような設計の場合には、内部告発の透明性が担保されないと不安に思われてしまいます。また、調査に時間がかかり、通報者に結果が返らない場合には、一度利用されても、それ以降の利用を期待できなくなるでしょう。
このような不安要素を残す「内部告発の環境」を改善するため、調査〜是正のフローをマニュアル化して配布するほか、進捗を通報者に定期的に報告するといった対策を取るのがおすすめです。また、第三者委員会を関与させて透明性を確保するのも安心につながります。
【注意点3】通報窓口が存在しても利用されない
通報窓口があっても、従業員に次のような印象を与えてしまうと制度が機能しません。
- 周知不足(ポスターや社内ネットワークで掲示がない)
- 対応が遅い(どうせ改善されないと不信がられてしまう)
- 保護に関する情報を伝えていない(通報しても匿名性が守られないと思われる)
従業員に正しく周知するためにも、入社時や定期研修で制度を説明するのがおすすめです。また、研修の際には実際に改善につながった事例を共有したり、経営層が積極的に制度を支持する姿勢を示したりすることで、利用率の向上につながります。
内部通報制度の導入に成功している企業事例

初めて内部通報制度を導入する場合には、導入に成功している企業事例から学ぶことが大切です。
ここでは、実際に内部通報制度を導入した企業の成功事例を解説します。
【成功事例1】不正の早期発見と被害拡大の防止
内部通報制度を整備したある食品メーカーでは、従業員からの匿名での内部告発により、在庫の不正計上が発覚しました。
この告発により、社内調査と処分、決算訂正が行われました。
内部告発によって早期にトラブルを抑えられれば、外部で大事になる前に損失を防止できます。
【成功事例2】大手製造業におけるデータ改ざんの早期発見
大手製造業において、社員からの内部通報により、製品の安全性に関わるデータ改ざんが発覚した事例があります。
役職にかかわらず利用できる制度が整備されていたことで、一人の社員が不正の事実を通報。調査の結果、通報内容が事実と判明し、法令違反などの重大な事態に発展する前に問題を是正できました。
この一件は、内部通報制度が企業の自浄作用を促し、信頼失墜のリスクを未然に防ぐ上で極めて有効であることを示す好例と言えます。
内部通報制度をプロに相談するメリット【必要なケース】

内部通報制度は自社だけで整備することも可能ですが、法的リスクや運用面の複雑さから、外部の専門家に相談するケースが増えています。
今回は以下に、プロに内部通報制度を相談するメリットを整理しました。
- 公益通報者保護法や個人情報保護法に適合した制度設計が可能になる
- 従業員が「報復を恐れず通報できる環境」を整備できる
- 社内のしがらみに左右されず、公平な調査・判断を提供できる
- 行政が発信するガイドラインの変更などにも、迅速に対応できる
社内ノウハウ・リソースがなく対応できない場合には、プロに相談するのが最適です。導入の失敗を防止したいなら、プロと協力して運用の質を高めてみてはいかがでしょうか。
内部通報制度の整備は「匿名型通報・相談窓口システム」がおすすめ

企業で匿名通報制度を整備したいと考えていませんか?スパイラルの「匿名型通報・相談窓口システム」を活用すれば、匿名性やデータの安全性を確保しながら、従業員が相談しやすい仕組みを整えられます。
匿名型通報・相談窓口システムの主な特長
- 1. プライバシーに配慮した「完全匿名性」
電話やメールと異なり、声やアドレスから個人が特定される心配がありません。相談者は完全に匿名状態を保ったまま、安心して通報・相談を行うことができます。 - 2. いつでもどこでも使える「マルチデバイス対応」
パソコン、スマートフォン、タブレットなど、利用するデバイスを問いません。インターネット環境さえあれば、相談者は時間や場所を選ばず、自身の都合の良いタイミングでアクセスできます。 - 3. 専門知識不要の「カンタン操作」
相談受付フォームには雛形が用意されており、システム設定に不安がある担当者でもスムーズに導入できます。相談者も直感的に利用できるため、システムの専門知識は不要です。 - 4. 証拠提出も可能な「ファイル添付機能」
相談時に、証拠となる文書や画像をフォームから直接アップロードできます。ExcelやPDF、画像ファイルなど、拡張子を問わずあらゆる形式のデータに対応しており、正確な事実確認をサポートします。
匿名型通報・相談窓口システムのお問い合わせ・資料請求はこちら
まとめ
内部通報制度は、単なる法令対応にとどまらず、企業の信頼性と持続的成長を守るための重要な仕組みです。
改正公益通報者保護法により、保護の対象が従業員だけでなく退職者や取引先の従業員などにも拡大され、幅広い関係者からの通報を適切に受け止める体制整備が求められています。もし自社で内部通報制度の設計や運用に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することやソリューションの導入を考えることが重要と言えるでしょう。