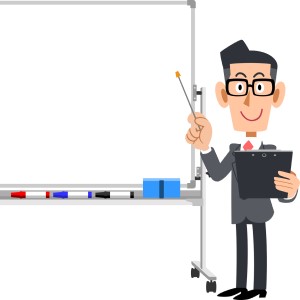匿名型通報・相談窓口システムの記事
ARTICLE会社の相談窓口とは?設置が必要な理由や機能させるポイントを解説

会社の相談窓口の設置において「運営方法がわからない」「効果があるのか不安」と躊躇している企業も多いでしょう。適切な設置・運営方法を理解すれば、従業員の安心感向上や職場環境の改善を実現できます。この記事では、会社の相談窓口の必要性や効果的な運営ポイント、よくある課題について解説します。
目次
会社の相談窓口とは?

会社の相談窓口とは、従業員が職場で抱えるさまざまな悩みや問題を気軽に相談できる場所のことです。具体的には、パワハラやセクハラといったハラスメント、仕事のストレス、人間関係の悩み、メンタルヘルス不調などについて相談を受け付けています。
会社の相談窓口が設置される背景には、従業員の心身の健康を守り、安心して働ける職場環境をつくりたいという企業の考えがあります。また2022年4月からは、ハラスメント防止対策として、中小企業も含めて相談窓口の設置が義務付けられました。
会社の相談窓口の役割は、従業員が一人で悩みを抱え込む前に適切なサポートを受けられる仕組みを整えて、職場全体がより働きやすい環境へと改善していくことです。
会社に相談窓口の設置が必要な5つの理由
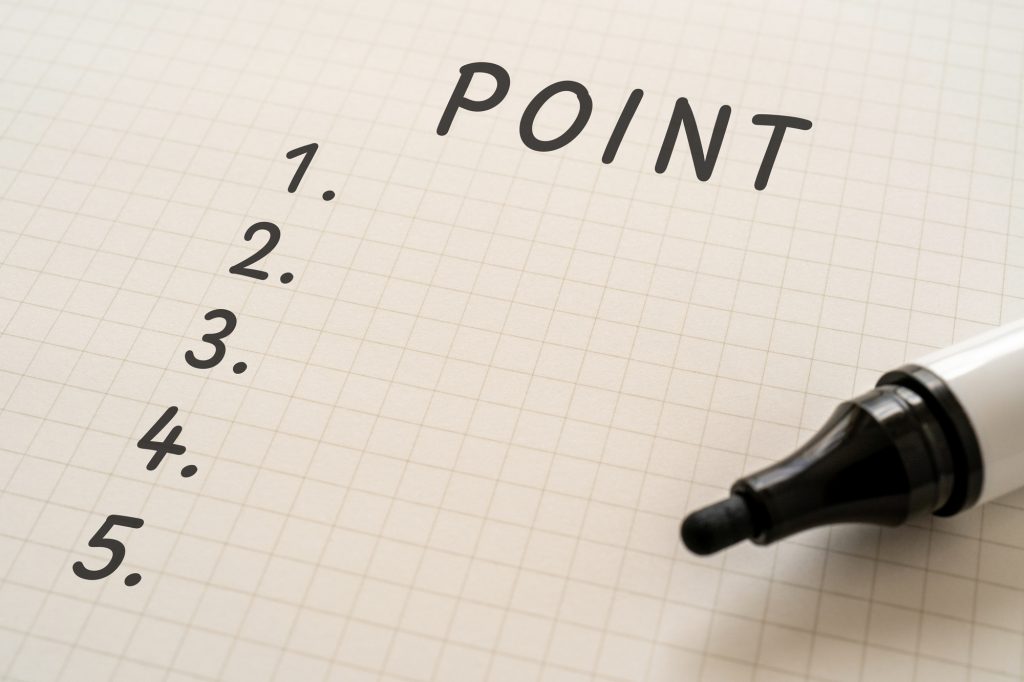
会社に相談窓口が必要な理由として、大きく以下の5つがあげられます。
- 法的義務への対応とコンプライアンス強化
- メンタルヘルス不調の早期発見と予防
- ハラスメント対策と職場環境の改善
- 従業員の安心感向上と信頼関係の構築
- 生産性向上と離職率の低下
順番に見ていきましょう。
理由1:法的義務への対応とコンプライアンス強化
前述したように、企業には法律によって相談窓口の設置が義務付けられています。企業が法的要求に対応できない場合は、行政指導や訴訟リスクも考えられます。しかし法的義務への対応は、単に法律を守るためだけではありません。
従業員の健康と安全を守るという本来の目的を理解し、企業の社会的責任を果たすことがなにより大切です。法令遵守は企業の信頼性を高め、社会から評価される組織へと成長するために必須の要素といえるでしょう。
理由2:メンタルヘルス不調の早期発見と予防
職場でのメンタルヘルスやストレスなどの問題は増加傾向にあります。なかでも2015年の「ストレスチェック制度」施行以降、労働者が気軽に相談できる環境を整え、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことが企業の重要な責務です。
このような現状で会社の相談窓口は、従業員が抱える問題を安心して相談できる場所として機能し、予防や早期発見、適切な対応まで一貫して担う役割を果たすのです。これらの取り組みにより、従業員の健康維持だけでなく、会社の生産性向上や離職率の低下にもつながるでしょう。
理由3:ハラスメント対策と職場環境の改善
現代の職場では、セクハラやパワハラといったハラスメントが深刻な社会問題となっています。またカスタマーハラスメント(カスハラ)も問題視されるなど、問題が職場内にとどまらず幅広いハラスメント対策が求められています。
そのため、会社の相談窓口を設置することで、ハラスメントの兆候を早期に発見し対処できるため深刻な事態を防げるようになるでしょう。
さらに、問題行動を早い段階で適切に対応することで、企業に与える影響を最小限に抑えられます。具体的には職場環境の悪化を防ぎ、企業全体の士気や業務効率を守る役割も期待できるでしょう。
理由4:従業員の安心感向上と信頼関係の構築
職場でなにか問題が発生したとき、自分が声をあげることで「不利益や報復を受けるのではないか」と不安を感じる従業員は少なくありません。しかし会社の相談窓口といった、匿名で気軽に相談できる場所があると、自分の悩みや不満を共有しやすくなり、従業員に安心感を与えられます。
また問題に対して真摯に向き合い、解決に向けて取り組んでいる姿勢が伝われば、従業員からの信頼感も高まるでしょう。信頼関係の構築によって職場内でのストレスや不安を軽減できるため、よりよい労使関係を築けるようになるのです。
理由5:生産性向上と離職率の低下
会社の相談窓口の設置は、従業員のモチベーション維持・向上に直結する取り組みです。仕事で行き詰まりを感じたり、人間関係に悩んだりした際に、相談できる相手や場所があることで、従業員は一人で問題を抱え込まずに済みます。迅速な問題解決が期待できることに加え、相談相手に話を聞いてもらうだけでも精神的な負担が和らぎ、職場での意欲を再び取り戻すケースも少なくないでしょう。
さらに従業員が抱える問題を早期に発見できれば、長期的な欠勤や退職防止などにもつながります。結果として、労働生産性向上やモチベーション維持などの効果が期待でき、企業全体のパフォーマンス向上に大きく貢献するでしょう。
会社の相談窓口が利用されにくい7つの理由

企業にとって必須の相談窓口ですが、利用されにくい理由として、以下の7つがあげられます。
- 相談窓口の存在や利用方法を知らない
- 相談しても問題が解決されないという不信感
- プライバシーが守られない・情報漏洩への不安
- 相談すること自体への心理的ハードルの高さ
- 報復や不利益な扱いを受ける恐れ
- 相談窓口の対応が不適切で機能していない
- アクセスの困難さや手続きの煩雑さ
順番に見ていきましょう。
理由1:相談窓口の存在や利用方法を知らない
まず根本的な問題として、従業員が相談窓口の存在そのものを知らないケースがあげられます。企業側では「きちんと設置している」と認識していても、実際には従業員への周知が不十分で、どこに相談すればよいのかわからない状況があるのです。また会社に相談窓口があると知っていても、具体的な利用方法がわからないという問題もあります。
「電話番号は知っているが、誰が対応するのかわからない」「どのような内容を相談できるのかわからない」といった不明瞭さが、利用をためらわせる要因となっています。さらに、オンラインサービスや24時間対応の窓口など、新しい形の相談手段はとくに広報が不足しがちで、せっかくの便利なサービスが活用されていない現状もあるのです。
理由2:相談しても問題が解決されないという不信感
多くの従業員が抱える不安は「相談しても結局なにも変わらないのではないか」という疑念です。過去に相談したが思ったような対応がされなかった経験などから、会社の相談窓口への不信感が生まれてしまうケースも。たとえば相談後に「人事部に伝えておきます」と言われただけで、その後の経過報告や改善策の提示がないケースです。
こうした対応では、相談者は「真剣に取り合ってもらえていない」と感じ、次第に相談窓口そのものに対する期待を失ってしまいます。企業側が「話を聞くだけです」という姿勢では、問題解決を求める相談者の期待に応えられず、制度があっても機能しない状況を生み出してしまうのです。
理由3:プライバシーが守られない・情報漏洩への不安
会社の相談窓口を利用する際の大きな懸念のひとつが、プライバシーの保護に関する不安です。
株式会社Smart相談室が行った調査によると、従業員の方は、相談窓口を活用していると思いますか。という質問に「あまりそう思わない」「全くそう思わない」と回答した方の43.0%が「相談内容を他人に知られてしまう可能性があるから」を利用しない理由としてあげており、最も多い回答となっています(※1)。
たとえば、会社の相談窓口が、人事部や総務部の担当者による兼任制の場合「普段の業務で関わりがある人に相談内容を知られたくない」という心理的な抵抗感が障壁となります。匿名性の確保や情報管理体制について明確な説明がなされていないと、従業員は安心して相談できないでしょう。
「Q6.従業員の方が相談窓口を活用していないと思う理由を教えてください。(複数回答)」(n=277)と質問したところ、「相談内容を他人に知られてしまう可能性があるから」が43.0%、「相談したい内容がプライベートな内容だから」が35.4%、「具体的に何を相談できるのかわからないから」が34.7%という回答となりました。
(※1)出典:PRTIMES|株式会社Smart相談室「【人事・労務担当者500名に調査】64.7%が積極的に活用できる社外相談窓口サービスの設置が「離職率低下につながる」と実感」
理由4:相談すること自体への心理的ハードルの高さ
「恥ずかしい思いをするのではないか」「こんなことで相談してもいいのか」などの不安も、会社の相談窓口の利用を踏みとどまらせる原因です。なかでもメンタルヘルスに関する相談では「カウンセリングを受ける=弱い人間」という偏見も影響しています。
また「相談窓口に行く=自分は深刻な問題を抱えている」という思い込みから、軽微な問題でも「そこまで深刻じゃないから」と相談を避ける場合も想定されます。
理由5:報復や不利益な扱いを受ける恐れ
ハラスメントの被害を受けている場合「相談したことが加害者に知られたら、さらにひどい扱いを受けるのではないか」「自分が異動させられたりしないか」といった不安を持つ従業員もいます。また「相談内容が人事評価に影響するのでは」「昇進や昇格に悪影響が出るのでは」という懸念も。
法律上は相談したことを理由とする不利益な取り扱いは禁止されていますが、実際に会社がそれを守ってくれるかどうかの保証が見えない限り、従業員は安心できません。こうした不安を解消するためには、企業側が報復防止の仕組みを整備して、それを従業員に示すことが必要です。
理由6:相談窓口の対応が不適切で機能していない
勇気を出して相談したにもかかわらず、会社の相談窓口の対応が不適切であるケースも多く報告されています。たとえば「事実関係が断定できないので対応不可です」「その問題はこちらの部署では受け付けておりません」といった対応があげられます。さらに問題なのは、相談窓口の機能や役割が明確になっていない状況です。
相談者は問題の解決を期待しているのにもかかわらず、話を聞いてもらうだけの対応になっているケースです。このような不適切な対応は、口コミとして広まり、ほかの従業員の利用意欲も削いでしまうでしょう。
理由7:アクセスの困難さや手続きの煩雑さ
多くの相談窓口が平日の限られた時間帯のみの対応となっており、忙しい従業員にとっては利用しづらい状況も理由のひとつです。「電話番号やメールの宛先が不明」「どのように相談したらよいかわからない」といった理由で、相談を諦めてしまうケースも見られます。
さらに、相談窓口にアクセスするための手続きが複雑すぎる場合も問題です。一部では「手続きが難しく相談するのが手間」という場合もあり、せっかくの制度が活用されない原因となっています。
会社の相談窓口を効果的に運営する7つのポイント

企業として、相談窓口を効果的に運営していくポイントとして、以下の7つがあげられます。
- 複数の相談方法を設ける
- 相談窓口の存在を積極的に周知する
- プライバシー保護と守秘義務を徹底する
- 相談員の専門性を向上させる
- 迅速で透明性のある体制をつくる
- 社外専門機関との連携を活用する
- フォローアップ体制を整備する
順番に解説していきます。
ポイント1:複数の相談方法を設ける
会社の相談窓口を効果的に機能させるためには、従業員一人ひとりの状況や性格に合わせた相談方法を用意しましょう。人によって相談しやすい方法は異なり、対面での面談を好む人もいれば、電話やメールでの相談を選ぶ人もいるためです。さらに匿名での相談が可能であれば、より多くの従業員が利用しやすい環境をつくり出せるでしょう。
ただし匿名相談の場合は、状況把握が難しくなる点に注意が必要です。また現代の働き方に合わせて、勤務時間外でも相談できる体制や、オンラインチャットなど新しい相談手段の導入も検討すべきでしょう。相談方法を多様化すれば、従業員の声をより早く、正確に把握できるようになり、職場の問題解決につながりやすくなります。
ポイント2:相談窓口の存在を積極的に周知する
会社に相談窓口を設置しても、従業員がその存在を認知していなければ意味がありません。
- 社内メール
- 掲示板
- 定期的な研修
といった手段を使って何度も伝える必要があります。周知の際は、単に窓口の存在を認知させるだけでなく、利用方法や相談可能な内容も示しましょう。また新入社員研修や管理職研修など、人が集まる機会に担当者から直接説明する場を設けると効果的です。
定期的に周知すれば問題発生時に「相談窓口で話してみようかな」と思い出してもらえるでしょう。
ポイント3:プライバシー保護と守秘義務を徹底する
従業員が安心して相談できるよう、相談内容や相談者の個人情報は厳重に管理し、本人の同意なく第三者に開示しないことを伝えましょう。また相談者のプライバシーを尊重し、個人が特定できる情報が拡散されないよう配慮することも欠かせません。
匿名相談の場合でも可能な限り事実確認を行い、職場改善につなげるための方針を定めておくべきでしょう。さらに重要なのは、相談したことやその事実関係の確認に協力したことを理由に、相談者や協力者の不利益にならないことを周知することです。
ポイント4:相談員の専門性を向上させる
相談窓口の効果は、対応する相談員の専門性と対応力に左右されます。
そのため、
- 専門的なカウンセラーやコンサルタントの配置
- 外部の専門家との連携
- 必要に応じた研修プログラムの提供
など、サポート体制を充実させることが重要です。
相談員は守秘義務を遵守し、公平・中立な立場で対応することが求められるため、これらの知識と技能を身につけるための継続的な教育が不可欠です。また相談窓口は単なる話し相手ではなく、従業員の問題解決や支援に積極的に関与する役割を果たす必要があります。
ポイント5:迅速で透明性のある体制をつくる
相談受付から解決までの流れを明確にして、
- 相談受付
- 関係者へのヒアリング
- 解決策の実施・フィードバック
といった一連の流れを定めましょう。なかでも重要なのは、相談内容をヒントに職場改善のPDCAサイクルを回すことです。
たとえば以下のような流れです。
- どんな相談が多いかを調べて、問題を見つける
- 見つかった問題に対して具体的な解決策を実行する
- 改善策の効果を確認し、結果を社内で共有する
- 改善の様子を目に見える形で示す
このサイクルをつづけることで、相談窓口は単なる話を聞く場所ではなく、職場全体が健康で働きやすい環境に保つための仕組みとして根付いていくでしょう。
ポイント6:社外専門機関との連携を活用する
人間関係への影響を懸念する声に対応するため、第三者機関による外部相談窓口の導入も検討しましょう。産業医や社労士といった専門家が対応すれば、相談しやすい環境をつくれるでしょう。また社外窓口を活用すれば、個人が特定されないように情報が伝達されるため、事実確認を取りやすいメリットもあります。
ポイント7:フォローアップ体制を整備する
相談窓口への相談が解決した後も、継続的にフォローすることが大切です。相談事案の処理が終わったあとに、同じような問題が再び起きていないか確認する取り組みです。また相談者が不利益な扱いを受けていないかもチェックしましょう。定期的な面談を通じて、従業員の状況を把握するといった対応です。
面談では解決した問題が再発していないか、新たな課題が生まれていないかを確認します。さらに、相談したことで職場での立場が悪くなったり、嫌がらせを受けたりしていないかも丁寧に聞き取ることが重要です。
会社の相談窓口の運用でよくある4つの課題

会社の相談窓口の運用でよくある課題として、以下の4つがあげられます。
- 担当者の負担増加とリソース不足
- 影響力のある人材への対応の困難さ
- 対応マニュアルや運用フローの不備
- 匿名相談への対応
順番に見ていきましょう。
課題1:担当者の負担増加とリソース不足
相談窓口の運用において、担当者の負担増加も深刻な問題だといえます。多くの場合、相談対応は本来の業務と兼任で行われるため、担当者にとって大きな負担となるためです。
さらに相談内容は複雑で専門的な知識が必要な場合も多く、適切に対応ができる人材の確保が難しい状況があります。加えて、相談対応のスキルや経験が不足している担当者では、「マニュアル的で親身に話を聞いてくれない」といった不満を持たれるケースもあり、窓口への信頼を失う原因となっています。
課題2:影響力のある人材への対応の困難さ
会社内で立場の強い人が問題を起こしている場合の対応も課題のひとつです。実際の調査では、約3割の企業が「役職者・年長者・影響力のある人材への指導が難しい」と回答しています(※2)。上司や管理職、会社の重役がハラスメントを行っている場合、社内の人間では対応や指導が困難なケースがあるのです。
相談を受けても、実際の改善につながらない場合が多く、相談者にとっては「話しても無駄」という失望感を与えてしまいます。このような状況では、外部の専門機関による第三者的な介入が必要になります。
前の質問で『社内にパワハラ相談窓口を設けている』と回答した方に、「社内にパワハラ相談窓口を設置してみて、どのような課題感を感じていますか?(複数回答可)※キーマン=影響力のある人材や、社内で期待されている人材のこと」と質問したところ、『相談者の情報が社内に漏れる(34.6%)』と回答した方が最も多く、次いで『行為者が役職者・年長者・キーマンで、指導が難しい(30.6%)』『担当者の負担が増える(28.3%)』『相談者が不利益になる(28.1%)』『行為者の情報が社内に漏れる(19.7%)』と続きました。
(※2)出典:PRTIMES|株式会社マイシェルパ「【社内相談窓口では難しい課題も?】約3割がパワハラに対する「役職者・年長者・影響力のある人材への指導が難しい」と回答」
課題3:対応マニュアルや運用フローの不備
相談窓口に寄せられた内容への対応が一貫しておらず、適切なフォローアップが行われないという課題もあります。「対応がマニュアル的」「会社にとって都合の悪い話はなかったことにされた」といった不満が従業員から出るケースです。相談を受けたあとの改善やフィードバックが一切行われない場合、勇気を出して相談した人も失望し、今後は相談しなくなってしまう悪循環が生まれます。
問題解決に向けた具体的なアクションプランと、相談者への継続的なフォローアップ体制が求められているのです。
課題4:匿名相談への対応
多くの従業員が匿名での相談を希望しますが、これには対応上の難しさも考えられます。たしかに問題を解決するためには事実関係の確認が必要であり、関係者からの聞き取りも欠かせません。しかし匿名相談では、相談者に追加の確認を取ることが難しく、対応を断られてしまう場合があるのです。
このジレンマを解決するためには、匿名性を保ちながらも効果的に問題解決ができる仕組みづくりが重要な課題です。
まとめ
会社の相談窓口は、法的義務であると同時に従業員に安心を与える重要な仕組みです。しかし設置しただけでは十分ではなく、プライバシー保護への不安や報復への恐れなど、従業員が気軽に利用できる環境づくりが欠かせません。
こうした課題を解消するには、専門的なITサービスの導入も有効です。たとえば、当社が提供している「匿名型通報・相談窓口システム」は、24時間365日対応可能なオンライン相談受付や、プライバシー保護・守秘義務を徹底したシステムが評価されています。
さらに匿名相談や報復防止策もサポートされるため、誰でも安心して悩みを伝えられます。導入を検討して従業員が働きやすい職場を実現しましょう。
匿名型通報・相談窓口システムの詳細はこちら

当社は、自社で開発・提供するクラウドサービス「SPIRAL®」を基盤として、「匿名型通報・相談窓口システム」を提供しています。
完全匿名性で1対1形式のため安心して相談できるのに加え、相談者も担当者もかんたん操作でご利用いただけます。
ハラスメント相談、コンプライアンス通報、育児介護休業法に基づく相談、女性特有の相談(フェムケア、健康経営)などさまざまなシーンでご活用いただけますので、さらに詳しく知りたいという方はぜひ以下URLをご覧ください。
サービスの詳細については「匿名型通報・相談窓口システム」のページをご覧いただくか、サービス導入をご検討中の方はこちらからぜひお問い合わせください。